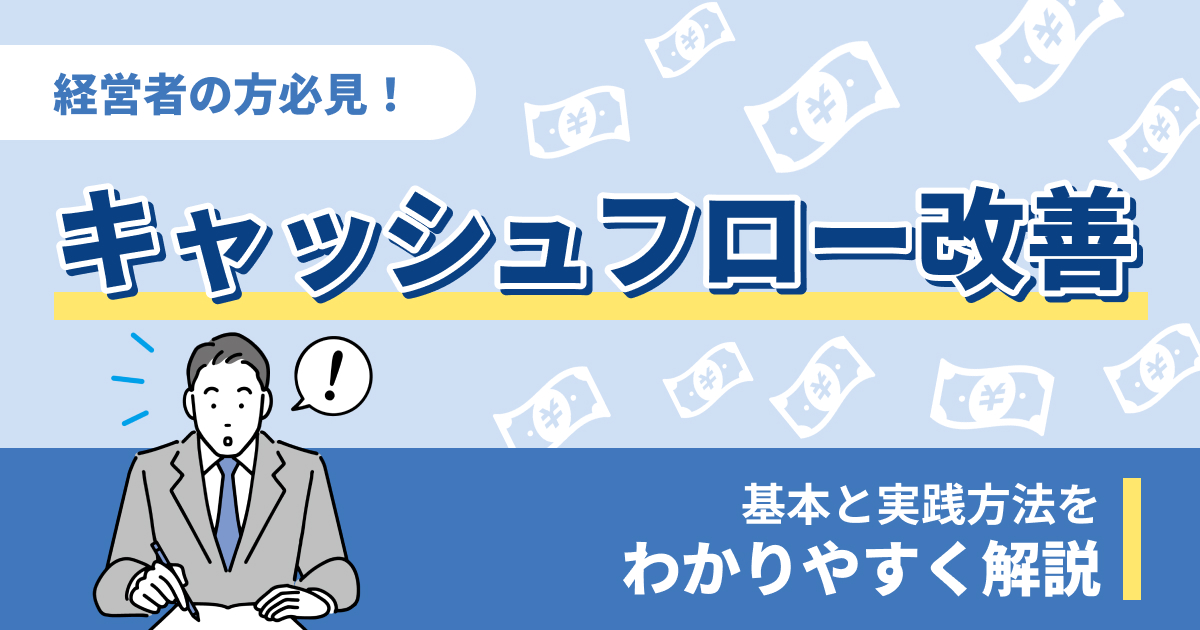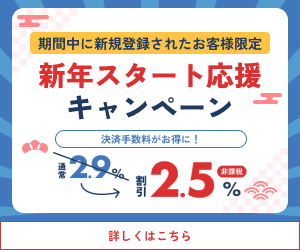業務を円滑に遂行し、いざと言うときの資金についても即時対応できるようにしておくことが重要です。急な資金調達に迫られた場合、融資を待っていては間に合いません。融資は最短でも半月かかります。
お金の流れ=キャッシュフローを改善することで、さまざまな事態に対応できるようになります。キャッシュフローを意識した「キャッシュフロー経営」を実践するためにも、今回はキャッシュフロー改善の基本と実践方法について解説していきます。普段キャッシュフローを意識していない事業主様もこれを契機にキャッシュフローの基本をぜひ学んでください。
キャッシュフロー改善とはお金の出入りの流れを良くすること
よく経営改善の際に言及される「キャッシュフロー」ですが、その中身について詳しく理解している人は少ないかもしれません。まず、キャッシュフローについて知っていただき、キャッシュフロー改善のためにどのようなことをすればよいのか考えてみましょう。
それぞれ順に解説します。
キャッシュフローとは実際のお金の動きを示す指標
キャッシュフローとは「お金の流れ」のことで、英語の「Cash(現金)」と「Flow(流れ)」を組み合わせています。事業においてある期間に現金や預金がどのくらい入ってきたか、または出ていったかを示します。具体的には、売上先からお金が入ってくる「キャッシュイン」から、支払先にお金が出ていく「キャッシュアウト」を差し引いた金額を指します。
売上や利益とキャッシュフローは異なります。たとえば、100万円掛売した場合、「売上」として計上している(資産)ものの、実際にお金が入ってきません。お金が入ってくるのは売掛金の支払い日です。
つまり、7月1日に100万円の売上があっても、それが掛売で回収日が8月31日の場合、約60日間「経理上売上があるのにキャッシュ(現金)がない状態」になります。
8月20日に80万円の資金需要があった場合、現金がないので支払えません。ここで不渡りを起こすと、いわゆる「黒字倒産」になります。帳簿上は売上があるのに、手持ち現金に変換されていないので、支払いができないのです。
一方のキャッシュフローは、実際の現金の動きを示すものです。人間の血液のように何かあれば速やかに「止血」できます。キャッシュフローが滞りなく流れていることで、さまざまな経営上の危機や日々の業務に対応できます。いざと言うときの「お守り」としてキャッシュフローが潤沢であることが重要な指標になります。
なおキャッシュフローの流れを数値化した「キャッシュフロー計算書」では、下記をそれぞれ分けて計算します。
- 営業活動によるキャッシュフロー
- 投資活動によるキャッシュフロー
- 財務活動によるキャッシュフロー
「営業活動によるキャッシュフロー」は本業による売上や支出による現金の動きを記したものです。これが一番重要になります。「投資活動によるキャッシュフロー」は有形固定資産の購入や売却、有価証券の売買など、将来の事業活動に影響を与える投資活動による現金の流れになります。設備投資が多ければマイナスですが、積極的に投資していることは必ずしも企業評価を下げません。
最後の「財務活動によるキャッシュフロー」は借入や返済、株式の発行や自己株式の取得など、資金調達や返済に関する現金の流れを表します。借入が増えてもプラスになりますし、返済(負債が減る)するとマイナスになります。財務活動によるキャッシュフローはプラスの場合評価されるものではないことに注意してください。
キャッシュフロー計算書を作成してようやく、他の財務諸表である貸借対照表と損益計算書では確認できない、会社の現金の動きを確認できます。
キャッシュフローを改善する4原則は基本的な考え
キャッシュフローを改善するための4つの原則は、企業経営における資金繰りの基本です。
- キャッシュインを早くする
- キャッシュインを多くする
- キャッシュアウトを遅くする
- キャッシュアウトを少なくする
これを徹底するのが基本になります。現金の入金を早く、多くして懐のキャッシュを潤し、逆に出金は遅く、少なくするのが大切です。言い換えると、売掛金の支払いサイトは短く、買掛金の支払いサイトは長くします。売上や仕入の帳簿上の金額ではなく、手元にあるお金をどのくらい増やせるのかが、キャッシュフロー改善のための重要なポイントになります。
キャッシュフローが悪化する主な原因を解説
キャッシュフローはなぜ悪化していくのでしょうか?キャッシュフロー悪化の原因は1つではなく、複数の要因が関係しています。みなさまの会社はどのキャッシュフロー悪化要因が多いのか、ぜひここでチェックしてください。
それぞれ順に解説します。
売掛金の現金化(キャッシュイン)まで時間がかかる
キャッシュフローが悪化する主な原因の1つ目は、「売掛金の現金化までに時間がかかること」が挙げられます。
企業が商品やサービスを販売した後、「掛売」とした場合、すぐに現金を受け取れるわけではなく、一般的には請求書を発行し、一定の支払サイト(例:30日、60日)を経て入金されます。この期間が長引くと、企業の手元資金が不足し、仕入れや人件費などの支払いに支障をきたす可能性があります。
特に取引先が大企業であったり、業界の慣習として支払サイトが長い場合(建設業など)、資金繰りが困難になることも少なくありません。さらに、売掛先からの入金遅延や回収不能(=不良債権化)が重なると、企業のキャッシュフローはさらに悪化し、事業継続に影響を及ぼすリスクが高まります。そのため、キャッシュフローの改善には、売掛金の回収期間(支払いサイト)を短縮する取り組みや、ファクタリングなどの活用が重要です。資金の出入りを的確に管理し、現金の回収タイミングを早める工夫が、安定した経営には欠かせません。
仕入れや経費などの支払い(キャッシュアウト)が先行する
キャッシュフローが悪化する主な原因の2つ目は、「仕入れや経費などの支払いが先行すること」です。多くの企業では、商品やサービスを販売するために、まず原材料や在庫を仕入れたり、人件費や外注費などの経費を支払ったりする必要があります。建設業で説明すると、実際に工事に取り掛かる前に、建築資材の仕入、一人親方などへの支払い、燃料の準備などが必要になります。先行投資しないと、仕事自体ができなくなっています。
これらの支払いは売上が発生する前に必要で、売掛金として入金されるまでの間に資金の空白が生じてしまいます。特に成長過程にある企業や、新規取引が増えている企業では、支出のタイミングが収入よりも早くなる傾向が強く、キャッシュフローが圧迫されやすくなります。また、仕入先や外注先への支払い条件が厳しい場合、売上の入金を待たずに現金で支払わなければならないケースもあり(有能な「一人親方」やフリーのSEへの支払いなど)、資金繰りに影響を与えます。
このような状況が続くと、たとえ利益が出ていても、現金(キャッシュ)が不足して経営が立ち行かなくなるリスクがあります。したがって、キャッシュアウトのタイミングを見極め、必要に応じて支払サイトの交渉や資金調達手段の活用を行い、健全なキャッシュフローを維持することが求められます。
設備投資などで多額の資金を一括支出してしまう
急にキャッシュアウトしてしまう原因として、設備投資などで多額の資金を一括支出してしまうことが挙げられます。分割払いにすればそうならないのかもしれませんが、案件によっては一括支出しないといけないものもあります。
高額の手付金(一時金)を支払って設備投資しなければならないこともあります。あるいは大型案件(公共事業など)で高額の仕入れを一気に行う必要がある、有能な「一人親方」で前払いで報酬を出すなど大きな仕事を請ける際に、どうしても一時的に支出が増えてしまい、それを一括で支払わなければならなくなることもあります。
公共事業でも仕入資金も含めて支払われるのは、工事が完了して検品、検収が終わってからのことが多く、その場合、キャッシュアウトが早く、かつ高額になってしまいます。そうなると、当然手持ちの現金が少なくなるので、キャッシュフロー悪化してしまいます。
借入金の元本返済や利息支払いが経営を圧迫している
キャッシュフローが悪化する主な原因の3つ目は、「借入金の元本返済や利息支払いによる資金圧迫」です。企業が資金調達を行う手段として借入は一般的ですが、その返済義務は毎月確実に発生します。特に返済額が大きかったり、複数の金融機関から借り入れを行っていたりする場合、固定的なキャッシュアウトが重くのしかかり、資金繰りを圧迫する要因となります。「財務活動によるキャッシュフロー」がプラスになると、キャッシュフローが悪化します。
加えて、金利の上昇局面では利息負担も増加し、利益が出ていても手元資金が減少してしまう状況が発生します。ゼロ金利、マイナス金利が撤廃された中では、今後返済利息が上がっていくことも予想されます。
加えて、売上の減少や売掛金の回収遅延などと重なると、返済原資の確保が難しくなり、最悪の場合は返済遅延や資金ショートに至るリスクもあります。返済遅延になれば信用情報に「×」が付き、以後の融資に大幅減点となります。
さらに、新規の設備投資や事業拡大のために借入が増加している企業では、将来の収益が追いつくまでの期間、返済の負担がキャッシュフローの足かせとなることもあるでしょう。そのため、借入額と返済計画のバランスを見直し、必要に応じて返済スケジュールの調整やリスケジュール交渉を行う(当然以後の融資にマイナスとなる)など、計画的で安定的な返済計画が必要になります。
そもそも赤字経営が続いていて営業利益が出ていない
キャッシュフローが悪化する主な原因の4つ目は、「赤字経営が続いており営業利益が出ていない」と言う状況です。営業利益は、企業の本業による収益から経費を差し引いたものであり、これが継続的に赤字であれば、現金収支にも悪影響を及ぼします。投資(投資活動によるキャッシュフロー)で補うのはかなり大変です。
赤字が続くと、日々の経費や支払いをまかなうために、手元の資金を取り崩さなければならず、キャッシュが徐々に減少していきます。やがて資金が底をつけば、借入や資産売却に頼らざるを得なくなり、さらなる負担やリスクを抱えることになります。
特に製造原価や人件費、地代家賃などの固定費が高い場合は、売上がある程度あっても利益が出ず、キャッシュフローも改善しにくくなります。また、売掛金の回収や在庫回転が鈍いと、さらに資金繰りが悪化します。
赤字経営が続く背景には、ビジネスモデルのミスマッチ、過剰な支出、価格競争などさまざまな要因があります。根本的な経営改善が必要になりますが、まずは収支構造を見直し、収益の改善に取り組むことが急務です。キャッシュフローの健全化には、まず安定した黒字経営をどう確立するかが重要です。
キャッシュフローを改善するには?9つの方法を解説
キャッシュフローを改善する、と言っても具体的に何をすればよいのかわからない方もいらっしゃるはずです。ここではキャッシュフローを改善する具体的な方法を9つ紹介します。
全部できればよいのですが、まず1つ2つから実践して、できるところからキャッシュフローを改善するプログラムを実行してみましょう。1つ改善するだけでもかなり変わってくるはずです。
それぞれ順に解説します。
売掛金の回収を早めて入金を加速させる工夫をする
キャッシュフローを改善するためには、売掛金の回収を早めて入金サイクル(売掛金回収サイト)を短縮することが非常に効果的です。多くの企業では、売上を計上していても、現金が手元に入るまでにタイムラグがあり、資金繰りを圧迫する要因となっています。これを改善するには、まず請求書の発行を遅らせないことが基本です。締め日から間を空けず即座に請求書を出すことで、入金までの期間を短縮できます。
また、取引先との交渉で支払い条件の見直しを行うことも有効です。たとえば、月末締め翌月末払いの条件を、翌月15日払いなどに変更できれば、現金化のスピードが上がります。
さらに、売掛金の一部を早期に回収できるファクタリングの活用も検討の価値があります。手数料はかかりますが、資金繰りを安定させる手段として有効です。売掛先にバレたくないなら2社間ファクタリング(手数料が高い)、売掛先にバレても良いなら3社間ファクタリング(手数料が安い)を行います。
その他、未回収の債権に対する催促を強化し、支払い遅延を防ぐことも重要です。入金の早期化は、キャッシュフロー改善の第一歩となります。
支払いサイトを延長して支出のタイミングを調整する
キャッシュフローを改善する手段の一つとして、買掛金の支払いサイトの延長があります。これは仕入先や外注先などへの支払い期限を後ろ倒しにすることで、手元に現金が長く残るように調整する方法です。入金と支出のタイミングにズレがある場合、たとえ黒字経営であっても資金繰りが苦しくなることがあります(黒字倒産の遠因)が、買掛金の支払いサイトを見直すことでそのギャップを埋めることが可能になります。
たとえば、従来「納品後30日以内に支払い」としていた条件を「60日以内」に変更できれば、月次のキャッシュフローにゆとりが生まれます。取引先との信頼関係がある場合は、こうした交渉も比較的スムーズに進むことが多いです。また、複数の支払いを一括で行わず、可能な範囲で分割払いにする方法もあります。ただし、交渉が一方的になると取引先との関係が悪化するリスクもあるため、誠実な姿勢での対応が求められます。
資金繰りに余裕を持たせるためには、入金を早めると同時に支出を遅らせると言う、両面のコントロールが重要です。支払いサイトの調整は、その中でも効果が高い戦略の一つと言えるでしょう。
税金や社会保険料の支払いスケジュールを調整する
キャッシュフローを改善する場合、税金や社会保険料の支払いスケジュールを見直すことも有効な方法の一つです。これらの支払いは金額が大きく、期日に一括で納めると資金繰りに大きな影響を与える可能性があります。しかし、状況によっては納付期限の延長や分割納付といった制度を活用でき、キャッシュフローの圧迫を緩和することが可能です。
たとえば、法人税や消費税は、税務署に相談、届出ることで「延納」や「分割納付」が認められる場合があります。特に一時的な資金難や災害、売上の急減などがあった場合には、納付期限の猶予が認められることもあります。
同様に、社会保険料についても、日本年金機構へ申し出れば、分割納付や延納の手続きが可能です。社会保険料を毎年7月末一括払いにすると、その後のキャッシュフローがきつくなりますが、毎月払いならばそこまでキャッシュフローは圧迫されません。
一括払いではなく、毎月払いにすることで、毎月の支出を平準化でき、手元資金の確保に役立ち、キャッシュフローが安定します。
ただし、分割払いや延納の手続きには申請書類の提出や審査が必要となるため、早めの準備が重要です。無断で支払いを遅らせれば「脱税」になり延滞金が発生するため注意が必要です。正規の手続きを踏めば税金や社会保険料の納付スケジュール毛変更はキャッシュフロー改善の有効な手段となります。
在庫を最適化してキャッシュの滞留を防止する
キャッシュフローの改善において、在庫の最適化は非常に重要な取り組みです。過剰な在庫は、商品が売れるまで資金が「在庫」と言う形で滞留してしまい、現金が手元から出ていったまま戻ってこない状態を生み出します。特に回転率の低い商品や季節性のある商品を大量に抱えてしまうと、キャッシュフローに大きな悪影響を与えることになります。売れない在庫は「不良在庫」(不良債権)になり、資産ではなく負債になってしまいます。
在庫を適切に管理するには、まず需要予測を正確に行い、必要な数量だけを仕入れる体制を整えることが求められます。販売データやトレンドを分析し、どの商品がどの時期にどれだけ売れるかを把握することで、無駄な仕入れを減らせます。
さらに、サプライヤーとの連携を強化し、小ロットかつ高頻度で仕入れができる体制を整えることで、在庫の圧縮と現金の流動性向上を図ることもできます。在庫の適正化は売上や利益の向上にもつながるほか、倉庫費用や廃棄ロスの削減にも寄与します。在庫は「見えにくい資金の滞留先」と言えるため、定期的な見直しを通じて、健全なキャッシュフローの維持に努めましょう。
固定費と変動費の見直しで支出を減らす方法を実践する
キャッシュフローを改善するには、固定費と変動費の見直しによって支出を抑えることが効果的です。特に固定費は毎月一定額が発生するため、利益が出ていなくても資金を圧迫します。代表的な固定費には家賃、人件費、通信費、光熱費、保険料などがあり、これらを削減することでキャッシュフローに大きな改善効果をもたらします。
たとえば、オフィスの規模を見直して賃料の安い場所に移転する、不要なサブスクリプションを解約する、保険のプランを適正化するといった方法があります。電気であれば、電力自由化によって「〇〇電力」以外の事業者と契約するなどです。また、人件費については、外部委託や業務効率化により正社員数を抑えることで、長期的な固定費削減につながります(ただ安易な人件費削減は副作用もあります)。
一方で、変動費は売上や業務量に応じて増減する支出で、原料費や広告費、配送費などが該当します。これらは日々の運用を見直すことでコントロールが可能です。たとえば、仕入れ先の見直しによる単価交渉、広告の費用対効果を分析した上での見直しなどが挙げられます。
固定費と変動費のバランスを把握し、コスト構造そのものを見直すことで、支出を無理なく抑えられます。こうした支出の見直しは、利益率の向上にもつながり、健全なキャッシュフローの実現に大きく貢献します。
資金調達を活用して手元キャッシュを一時的に増やす
キャッシュフローを改善する方法の一つに、資金調達を活用して一時的に手元資金を厚くすると言う手段があります。売上があっても入金までに時間がかかる場合や、急な支払いが重なって資金が一時的に不足する場面では、外部からの資金導入によってキャッシュフローを安定させることが可能です。
資金調達にはいくつかの方法があり、代表的なものは金融機関からの融資です。日本政策金融公庫や地方銀行、信用金庫などを活用すれば、比較的低金利で資金を確保できるケースもあります。資金調達は一義的には融資を受けられないか考えます。
また、設備投資や拡大したい事業によっては、補助金や助成金の対象となる場合もあります。こうした制度をうまく活用すれば、返済負担を抑えつつ資金調達が可能です。ただし、補助金も助成金も「後払い」なので事業実施時は自腹で費用を捻出する必要があります。
近年では、ファクタリングやクラウドファンディングなど、多様な資金調達手段も注目されています。特にファクタリングは、売掛債権を現金化することで借入とは異なる形で資金を得られ、キャッシュフローの改善に役立ちます。融資ではないので、信用情報照会もなく、利用歴が信用情報に記載されることもありません。
ただし、資金調達はあくまで一時的な対策であり、根本的なキャッシュフロー改善にはなりません。一時的に「輸血」(あるいは「点滴」)をしても、根本的な体質改善にはつながらないからです。
調達した資金を有効に使い、事業の効率化や売上の拡大、支出の見直しなど根本的な企業の体質改善を成し遂げることが大切です。
収益性を高めて中長期的にキャッシュを増やす
キャッシュフローを中長期的に改善するためには、収益性を高めることが最も根本的かつ持続的な対策となります。単に一時的な資金繰りを整えるだけでなく、安定した現金収入を生み出せる体質に企業を変えていくことが重要です。収益性の向上とは、売上を拡大するだけでなく、利益率を高める工夫を行うことを意味します。
具体的には、高付加価値の商品やサービスの開発・提供を進めることが効果的です。競合他社との差別化を図り、価格競争に巻き込まれずに適正な価格で販売できれば、収益性は大きく向上します。
同時に、業務の効率化や無駄の削減によって、コストを抑えながら利益を確保することも大切です。ITツールの導入や業務フローの見直しにより、経営改善を図り、人的・時間的コストを削減し、限られた投資で最大の成果を上げる体制を構築しましょう。
収益性の改善には一定の時間がかかりますが、結果として安定したキャッシュフローを生み出す基盤になります。経営の持続性を高めるためにも、目先の数字だけでなく、利益体質への転換を意識した戦略的な取り組みが求められます。
支払い時期を分散・平準化して資金繰りの波を小さくする
キャッシュフローを安定させるためには、支払いの時期を分散・平準化することが効果的です。多くの企業では、月末や特定の日に支払いが集中しがちですが、これが原因で一時的に資金が不足し、キャッシュフローが乱れるケースがあります。特に固定費や仕入費用、人件費、税金などが同時期に重なると、たとえ利益が出ていても手元資金が枯渇するリスクがあります。
このような事態を防ぐためには、支払いスケジュールを見直し、可能な範囲で支出のタイミングをずらす工夫が求められます。買掛金の支払いサイトの、見直しが重要になります。
具体的には、複数の仕入れ先との支払い期日を月内でずらして設定する、リース料や外注費の引き落とし日を分けるなどの対応が考えられます。
また、支払いのタイミングを把握しやすくするために、月次の資金繰り表やキャッシュフロー計算書を作成して、いつ・いくらの支出が発生するのかを可視化することも有効です。支払いの山を小さく分けて平準化することで、月内の資金の流れが安定し、資金ショートのリスクを軽減できます。
支出の集中を避けることは、経営の安全性を高め、計画的な資金運用を可能にするための基本です。支払い管理の徹底は、健全なキャッシュフローを維持するための重要なステップと言えるでしょう。
請求書や社会保険料をクレカ払いできるゆとりペイを使う

ゆとりペイのような「請求書カード払い」サービスの活用です。通常、請求書払いや社会保険料などの公的な支払いは銀行振込が一般的で、支払い期日が固定されているため、資金繰りに余裕がない企業にとっては大きな負担となります。しかし、ゆとりペイを使えば、こうした支出をクレジットカードで支払えるようになり、実際の資金の引き落としを最大で約1〜2か月先まで先延ばしにすることが可能です。請求書カード払いによって、実際に口座から落ちる日を30日~60日先延ばしにできます。
これにより、手元資金の流出を一時的に抑えられ、その間に売掛金の回収などで現金を補填する余裕が生まれます。特に、資金の動きが読みにくいスタートアップ企業や小規模事業者にとっては、キャッシュフローの平準化に大きく貢献します。また、カードによってはポイント還元やマイルの付与などもあり、経営にプラスとなる一面もあります。
さらに、ゆとりペイは社会保険料と言う通常カード払いができない費目にも対応しており、資金繰りが厳しいときに役立ちます。短期的な資金不足をしのぐだけでなく、毎月の資金計画を立てやすくなり、安定した経営にもつながります。なお、社会保険料の正規雇用は可能ですが、税金のカード払いはできないのでご注意ください。
ゆとりペイなどの「請求書カード払い」を賢く活用すれば、キャッシュフローの改善に役立ちます。
キャッシュフローを改善するメリットを具体的に解説
キャッシュフローの改善が経営にとって大きくプラスになる理由を本記事で詳しく解説しています。キャッシュフローを改善するデメリットはないので、ぜひチャレンジしてみてください。
それぞれ順に解説します。
資金繰りの不安がなくなり本業に集中できる
キャッシュフローを改善する最大のメリットは、資金繰りに対する不安が解消され、本業に専念できるようになる点です。日々の支払いに追われていると、資金調達に奔走することとなり、取引先との関係維持や新規案件への対応、商品・サービスの品質向上といった本来注力すべき業務に集中できなくなります。
特に中小企業や個人事業主にとって、資金ショートのリスクは常に頭をよぎる問題ですが、キャッシュフローが安定すれば、精神的な負担も大きく軽減されます。不安がなくなればより攻めの経営にトライできます。
また、資金に余裕がある状態が続けば、タイミングを逃さずに投資や仕入れ、採用といった攻めの経営判断を行うことも可能になります。結果として事業の成長スピードが加速し、収益性の向上にもつながります。資金の流れを整えることは、経営の安定だけでなく、将来の発展にも直結する重要な取り組みと言えるでしょう。
経営判断や設備投資の決断がスムーズになる
事業を運営していると、一気に多額のお金を使って新しい仕事を取る、あるいは大きな設備投資をすることで、前途が大きく拓けることがあります。大型の公共工事や公共システムの受注の際には、一時的に多額のキャッシュが必要になります。
融資を待っているとそれらの受注に間に合わない可能性もあります。ファクタリングなどを使って資金調達することもできますが、1000万円の売上があってもファクタリングでは800万円~900万円しか資金化できず、100万円超を手数料として支払うことになり、本来キャッシュとして手に入るお金を失います。
キャッシュフローが潤沢で、自己資金があれば、融資やファクタリングを頼らずに一気に勝負をかけられます。重大な経営判断や設備投資が融資の結果次第になってしまっては、刻一刻と動く状況に対応できません。キャッシュフローを改善するメリットはここにあります。
急な支出や予期せぬトラブルにも対応できる
キャッシュフローを改善することで得られる大きなメリットは、急な支出や予期せぬトラブルに柔軟に対応できる点も挙げられます。事業運営においては、設備の故障や取引先からの支払い遅延、突発的な仕入れ増加、原料費の急な高騰など、想定外の出費が発生することが少なくありません。手元資金が不足していると、こうした緊急事態に対応できず、事業活動が停滞したり信用問題に発展するリスクがあります。融資を待っていてはこれらの危機に間に合いません。
キャッシュフローが健全であれば、自己資金として一定額を確保できるため、急な支出があっても資金繰りが何とかなります。これにより、必要な支出が間に合い、リスクを最小限に抑えることが可能です。結果として、経営の安定性が高まり、長期的な事業継続にとって大きくプラスになります。
融資をはじめ金融機関や取引先からの信用が向上
キャッシュフローが改善されると、融資をはじめとした金融機関や取引先からの信用が大きく向上します。安定した資金繰りは企業の健全な経営状態を示す重要な指標であり、金融機関は融資の判断材料としてキャッシュフローの状況を重視します。キャッシュフローが良好であれば、返済能力が高いと判断され、融資審査が通りやすくなるほか、金利や融資条件の優遇を受けられる可能性も出てきます。
また、取引先にとっても、支払い遅延のリスクが低い企業は安心して取引を継続できるため、信頼できるビジネスパートナーになり得ます。新たなビジネスチャンスや取引拡大の可能性も広がり、成長を後押しします。
結果的に、キャッシュフローの改善は資金調達や取引条件で有利な立場を築けるため、経営の安定と発展に大きく貢献するメリットがあります。
黒字でも倒産するリスクを未然に防げる
キャッシュフローを改善することは、黒字経営であっても倒産リスクを未然に防ぐ上で非常に重要です。利益が出ていても、実際に手元に現金がなければ支払いが滞り、取引先や金融機関からの信用を失う恐れがあります。「売上」があっても未回収で手元にキャッシュがなく、支払いができないと「黒字倒産」の危機です。
健全なキャッシュフローを維持することで、利益とは別に常に十分な「遊び」の現金を確保でき、支払い遅延や突発的な出費にも対応可能になります。これにより、資金繰りの問題による黒字倒産リスクを大幅に減らせます。つまり、キャッシュフローの改善は単なる資金繰りの安定だけでなく、企業の存続を守るための生命線と言えるかもしれません。売上に加えてキャッシュフローをしっかり把握することが経営の安定に直結します。
キャッシュフロー改善に関するよくある質問
キャッシュフローを改善することで経営には大きなメリットがあります。そのためのキャッシュフロー改善方法について、よくある質問とその回答をお知らせします。みなさまの疑問が少しでも晴れれば幸甚です。
- キャッシュフローが良い企業とはどんな状態ですか?
-
キャッシュフローが良い企業とは、収入と支出のバランスが取れ、安定的に現金が常に手元にあるる状態の企業を指します。具体的には、営業活動によって得られるキャッシュ(営業活動によるキャッシュフロー)がプラスで、日々の仕入れや人件費、家賃などの支払いを十分にまかなえている状態です。
売掛金の回収がスムーズで、回収遅れがなく、在庫の管理も適切に行われており、現金が滞留することなく流れているのが特徴です。
また、借入金の返済や利息支払いが過度に経営を圧迫せず、自己資本比率も健全な水準にあることが多いです。こうした企業は、突発的な支出や経済環境の変化にも柔軟に対応できる資金の「遊び」があり、安定した経営基盤を持っています。
キャッシュフローが良い企業は、金融機関からの信用も高くなり、資金調達も容易になります。結果、新しい投資や事業拡大にも前向きに取り組むことが可能です。つまり、現金の流れが健全で、内部でしっかりと現金が循環している企業こそが、キャッシュフローの良い企業になります。
- 個人でもキャッシュフロー改善は可能ですか?
-
答えは「イエス」です。個人でもキャッシュフローの改善は十分に可能です。個人でのキャッシュフロー改善でまず重要なのは、毎月の収入と支出を正確に把握することです。家計簿アプリや会計ソフトを使って、固定費(家賃・光熱費・保険料など)と変動費(食費・交際費・娯楽費など)を見える化し、無駄な出費を見直します。
また、サブスクの解約や通信費の見直し、クレジットカードの使い過ぎを防ぐことも有効です。ファイナンシャルプランナーによる支出の見直しや保険の見直しと似ています。
キャッシュアウトを減らすことが重要ですが、もちろんキャッシュインも増やしてください。副業や投資による収入増加も、キャッシュフロー改善に大きく貢献します。支出を抑え、収入を増やす工夫を積み重ねることで、毎月の黒字化が実現し、キャッシュフローが改善します。事業関係ない支出の見直し、家計改善に近いのですが、個人の努力でもある程度キャッシュフローは改善できます。
- キャッシュフロー経営は時代遅れなのでしょうか?
-
キャッシュフロー経営は決して時代遅れではなく、むしろ現代の不確実、不透明な経済環境において、ますます重要性が高まっています。かつては売上や利益に注目する経営がメインストリームでしたが、現在では「現金がなければ企業は倒れる」と言う認識が広まり、キャッシュフローを重視する経営スタイルが定着しつつあります。
たとえ帳簿上は黒字でも、現金が不足すれば仕入れや給与の支払いができず、経営が立ち行かなくなる(=黒字倒産)ケースも少なくありません。特にコロナ禍や原材料高騰などを経て、外的要因による急な収支悪化を体験しました。
急な環境変化に対応するには、日頃からキャッシュの流れを可視化し、お金の流れを俯瞰しておくことが大切です。これは健康診断でご自身の血液(身体を循環するフロー)の状態を把握しておくことと似ています。血液ドロドロでは動脈硬化や循環器系の病気を起こしていきなり命の危機になることもあります。だから、企業の「血液」であるキャッシュフローを知ることが大切なのです。
また、成長のための投資や借入返済を計画的に行うにも、キャッシュフロー経営は有効な指針となります。IT技術の進展により資金管理もより正確・迅速にできるようになった今、キャッシュフロー経営は時代に合った、実践すべき経営手法と言えるでしょう。