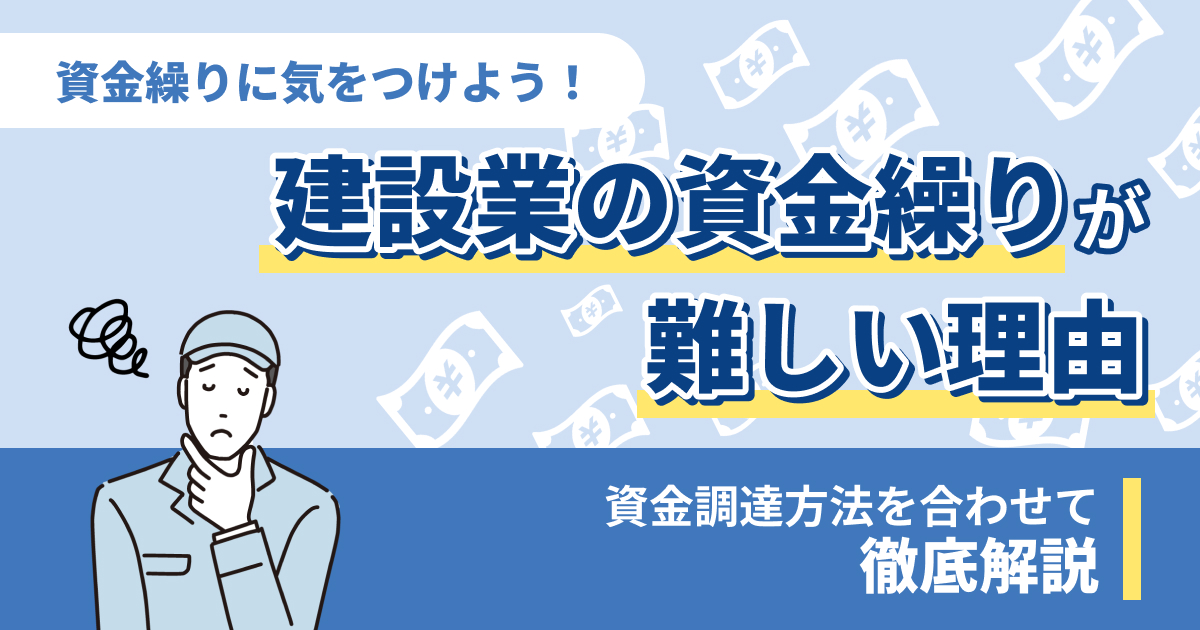建設業界は他の業界に比べて資金繰りが厳しいと言われています。業界特有の構造的な課題が存在していたり、社内の管理不足や内部問題が原因だったりします。資金繰り表とキャッシュフロー管理で先行きを見える化や赤字案件の回避などで資金繰り改善を進められる傾向にあります。
しかし、「具体的に建設業の資金繰りが厳しいと言われている理由は何?」「建設業におすすめの資金調達方法や避けるべき方法を知りたい」などの疑問が出てくるでしょう。
そこで本記事では、建設業の資金繰りが厳しくなる理由や建設業の資金繰りを改善するための具体策を解説します。建設業におすすめの資金調達方法や資金繰りが失敗する理由、よくある質問もまとめているため、気になる人はぜひ参考にしてください。
建設業の資金繰りが厳しくなる理由を解説
建設業は他の業種と比べて資金繰りが難しいと言われています。資金繰りが厳しいと言われる理由は、受注から入金までの期間が長く、支出が先行する特性があるためです。工事を始める段階で材料費や人件費などのコストが発生しますが、発注者からの入金は工事完了後や検収後に行われることが多いため、手元資金が不足しやすくなります。
また、元請けから下請けへの支払い期日が短い一方で、発注者からの入金が遅れるケースもあり、資金の流れが不安定になりやすい点も特徴です。
さらに、景気の変動や公共事業の予算削減など、外部環境に大きく影響を受けやすい業界のため、受注量が減少すると固定費の負担が重く、資金繰りは一層厳しさを増します。その他、業界特有の資金循環の遅さや不安定さが、建設業における大きな課題と言えます。
ここでは、建設業の資金繰りが厳しくなる理由を詳しく解説します。
業界特有の構造的な課題が資金繰りを難しくしている
建設業界の資金繰りが厳しい理由として、業界特有の構造的課題が挙げられます。工事の代金回収までの期間が非常に長く、建設工事は着工から竣工まで数か月、大規模なものでは数年に及ぶことも珍しくありません。この間も人件費や資材費、外注費などの支払いは継続的に発生しますが、工事代金は完成後や部分的な完成後に支払われる出来高払いが一般的です。先行して多額の費用支出が発生し資金を自社で賄う必要があります。
また、業界の慣行として残る手形取引も負担として挙げられます。現金化までに数か月を要する手形での支払いが多いと、売上は立っているのに手元に現金がない状況に陥りやすいです。
さらに、元請けから一次下請け、二次下請けへと続く重層的な下請け構造も問題とされています。下位の企業になるほど、中間マージンが抜かれて利益率が低下し、支払いサイトも長くなる傾向にあり、資金繰りはより厳しくなります。これらの構造的な問題が、建設業のキャッシュフローを常に不安定にさせていると言えるでしょう。
社内の管理不足や内部問題が資金繰りをさらに悪化させる
業界特有の構造的な課題に加えて、社内の管理体制の不備が資金繰りの悪化に影響を与えるケースも少なくありません。特に中小企業において顕著なのが、どんぶり勘定による経営です。個々の工事現場でどれくらいの利益が出ているのかを正確に把握せず、会社全体の資金の流れだけで判断していると、赤字工事の発生に気づくのが遅れてしまいます。防ぐためには、工事ごとに詳細な実行予算を作成し、実際の原価との差異を常に管理する体制が不可欠です。
また、実行予算の管理が甘いと、予期せぬコストの発生に対応できず、最終的に利益を圧迫し、資金繰りを悪化させることになります。
営業部門と工事部門の連携不足も問題とされています。営業担当者が採算度外視で安値受注をしてしまうと、工事部門がどれだけ努力しても利益を出すことは困難でしょう。受注段階で適切な利益を確保できるような見積もりの精度を高め、社内全体で情報を共有する仕組みが求められます。外部環境だけでなく、自社の経営管理体制を見直し、改善していくことが、厳しい資金繰りを乗り越えるためのポイントと言えるでしょう。
建設業の資金繰りを改善するための具体策を解説
建設業は資金繰りが厳しくなりやすい業界ですが、適切な管理と工夫を行うことで資金繰りの改善は可能です。資金の流れを正確に把握し、先行きを見通せる体制を整える必要があります。その上で、支払条件の見直しや資金の流出を抑える工夫を組み合わせることで、資金繰りの安定化を図れます。
また、収益性の低い案件を避け、利益を確実に確保できる案件に集中することも重要です。さらに、外注費や在庫管理を徹底して無駄なコストを削減することで、資金を守ることができます。具体的に建設業の資金繰りを改善させるポイントは、以下のとおりです。
それぞれ順に解説します。
資金繰り表とキャッシュフロー管理で先行きを見える化する
建設業の資金繰り改善において、基本的な対策として資金繰り表の作成と活用が挙げられます。資金繰り表とは、将来の現金の収入と支出を月ごとに予測し、一覧にした資料です。資金繰り表を作成することで、漠然とした不安ではなく、具体的な数字に基づいて「いつ、いくら資金が不足する可能性があるのか」を数か月先まで見通せます。支出の見える化が、的確な対策を打つための土台となります。
例えば、3か月後に資金ショートの可能性があると予測できれば、事前に金融機関に融資の相談をしたり、入金予定の前倒しを交渉したりと、余裕を持って行動を起こせます。資金が尽きてから慌てて対策するのとは雲泥の差で、スムーズな対応を実現します。
また、資金繰り表を毎月更新し、予測と実績の差異を分析することで、自社の資金繰りの癖や問題点が浮き彫りになります。例えば、特定の時期にいつも資金が厳しくなる、特定の取引先からの入金が遅れがちである、といった課題が明確になれば、より具体的な改善策へと繋げられます。日々の記帳だけでなく、未来のキャッシュフローを管理する意識を持つことが、安定経営のポイントと言えるでしょう。
支払サイトの交渉や条件見直しで出金負担を軽減する
キャッシュフローを改善するには、入金を増やす努力と同時に、出金をいかにコントロールするかが極めて重要です。有効な手段として、資材の仕入れ先や外注先の協力会社に対する支払サイトの交渉が挙げられます。建設業界は工事代金の入金まで時間がかかるため、支出のタイミングを可能な限り入金時期に近づけることで、手元資金の負担を大幅に軽減できます。
例えば、これまでの月末締め・翌月末払いの条件を月末締め・翌々月払いに変更してもらうよう交渉するだけでも、資金繰りには大きな余裕が生まれます。一方的な要求は取引関係を損なう可能性があるため、普段から良好な関係を築き、誠実な交渉が重要です。
また、支払サイトの延長だけでなく、取引量の増加を条件に単価の引き下げを交渉したり、複数の業者から見積もりを取ってコストを見直したりすることも、支出を抑える上で効果的です。地道な交渉や見直しを一つひとつ積み重ねていくことで、会社全体のキャッシュフローは着実に改善されます。支払業務を単なる作業と捉えず、資金繰りを安定させるための重要な戦略と位置づけて取り組むことが求められるでしょう。
在庫・外注費の管理強化で赤字案件を回避して資金を守る
個々の工事案件で利益を確保できなければ、会社全体の資金繰りが改善することはありません。特に一つの赤字案件が経営に与えるダメージは大きく、防ぐためには工事ごとの厳格な原価管理が不可欠です。中核となるのが実行予算の管理が挙げられます。実行予算とは、受注した工事を完成させるために必要な原価を、項目ごとに詳細に見積もったものです。重要なのは、予算を立てるだけでなく、工事の進捗に合わせて予算と実績の差異を常に監視し続けることです。
例えば、資材の仕入れ価格が想定を上回ったり、追加の外注費が発生したりした場合、すぐにその差異を把握し、原因を分析して対策を講じる必要があります。予実管理を徹底することで、赤字の兆候を早期に発見し、損失を最小限に食い止めることが可能になります。
また、現場に余分な資材を置きすぎないよう在庫管理を適切に行うことも、無駄な支出を減らし、資金の固定化を防ぐ上で重要です。地道な管理体制の強化こそが、不採算工事をなくし、会社の貴重な資金を守るための確実な方法と言えるでしょう。
収益性の高い案件に集中して資金繰りを改善する
資金繰りを根本的に改善し、会社を成長させていくためには、目先の売上だけを追うのではなく、どの案件で利益を生み出すかの戦略的な視点が欠かせません。収益性の高い案件に経営資源を集中させる必要があります。そのためには、自社が手掛けた過去の工事データを分析し、どのような種類の工事やどのような顧客からの案件が高い利益率をもたらしているのかを正確に把握しましょう。
例えば、特定の工法を得意としていたり、特定のエリアで強みを発揮していたりする可能性があります。他社にはない自社の強みを明確にし、特定領域の案件を積極的に獲得するための営業活動を展開するのも重要です。利益率の低い案件は、たとえ売上規模が大きくても、多くの手間と時間を費やした結果、手元にほとんど資金が残らないという事態に陥りがちです。予期せぬトラブルで赤字になるリスクも抱えています。
勇気を持って利益の薄い案件から撤退し、その分のリソースを自社が得意とする高収益な分野に振り向けることで、会社全体の利益率が向上し、キャッシュフローは着実に増加するでしょう。
建設業におすすめの資金調達方法を効果的に活用
建設業は入金までの期間が長く、工事開始時点から材料費や人件費といった支出が先行するため、資金繰りに苦労する企業が少なくありません。業界の特性を踏まえると、状況に応じて複数の資金調達方法を組み合わせ、効果的に活用することが重要です。銀行融資や保証制度といった長期安定的な資金調達に加え、ファクタリングのように売掛金を早期に資金化できる手段もあります。
また、近年は「請求書カード払い ゆとりペイ」のようなサービスを使い、支払期日を柔軟にコントロールする方法も存在します。これらをバランスよく利用することで、突発的な資金不足や支払いのタイミングのズレを解消しやすくなります。資金調達方法は一つに依存するのではなく、事業規模や資金需要の性質に応じて最適化することが、安定した経営基盤の構築につながります。建設業におすすめの資金調達方法や効果的な活用方法は、以下のとおりです。
それぞれ順に解説します。
銀行融資や保証制度で長期安定的な運転資金を確保する
企業の資金調達における基本的な選択肢として、金融機関からの融資があります。特に建設業のように、工事の先行投資で多額の運転資金が必要となる業種にとって、銀行融資は事業の根幹を支える安定的な資金源と言えます。融資のメリットは、ファクタリングなどの他の手法に比べて金利が低く、返済期間も長期に設定できるため、月々の返済負担を抑えながら計画的な資金繰りが可能になる点です。
また、会社の信用力が審査の基盤となるため、融資実績を積み重ねること自体が社会的な信用につながります。しかし、審査には事業計画書や決算書などの提出が必要で、時間もかかるため、急な資金需要には向いていません。銀行独自の融資であるプロパー融資の審査が厳しい場合には、信用保証協会の保証を付けて融資を申し込む保証付き融資が有効です。万が一返済が困難になった場合に保証協会が代位弁済を行う制度で、金融機関のリスクを低減させるため、融資のハードルが下がります。先行きの設備投資や安定的な事業運営のために、まずは銀行融資や保証制度などの公的な制度の活用を検討しましょう。
ファクタリングを利用して売掛債権を早期に資金化する
建設業界の大きな課題である入金サイトの長さを解決し、迅速に資金を確保する方法としてファクタリングが挙げられます。ファクタリングとは、工事代金などの未回収の売掛債権(請求書)をファクタリング会社に買い取ってもらうことで、本来の支払期日よりも早く現金化する金融サービスです。ファクタリングのメリットは、依頼してから入金までのスピードです。申し込みから最短で即日、数日中には資金を得られるため、急な材料費の支払いや人件費の確保など、突発的な資金需要に柔軟に対応できます。
また、ファクタリングは融資とは異なり、借入ではないため、貸借対照表上の負債が増えないオフバランス化が可能です。自己資本比率を悪化させることなく資金調達ができるため、銀行融資の審査にも影響を与えにくいメリットもあります。審査の対象は、自社の信用力よりも売掛先の支払い能力が重視されるため、赤字決算や税金滞納といった状況でも利用しやすいのが特徴です。手数料は発生しますが、黒字倒産のリスクを回避し、キャッシュフローを円滑にするための有効な手段と言えるでしょう。
請求書カード払い ゆとりペイで支払いを柔軟にコントロール

キャッシュフロー改善のためには、収入を早めるだけでなく、支出のタイミングを遅らせることも重要です。支払いの先延ばしを実現する方法として「請求書カード払い ゆとりペイ」がおすすめです。通常は銀行振込で支払うべき外注費や資材費などの請求書を、自社が保有する法人カードや個人事業主向けのビジネスカードで代わりに決済できる仕組みです。
サービス会社がまず取引先に振込を行い、自社は後日クレジットカードの引き落とし日に利用額を支払います。サービスの最大のメリットは、実質的な支払いサイトを最大で60日程度延長できる点です。手元の現金を温存しながら支払いを済ませることができ、急な資金需要が発生した際にも柔軟に対応できます。
銀行融資のように複雑な審査や担保は不要で、オンラインで手軽に申し込めるため、必要な時にすぐに利用できる機動性も魅力です。ファクタリングと組み合わせることで、入金と支払いの両面から資金繰りを最適化し、経営の安定性を高められるでしょう。
建設業の資金繰りで失敗する事例と避けるべき行動
建設業において、資金繰りは事業継続の重要なポイント。どれほど多くの案件を受注し、売上を計上しても、手元の資金が不足すれば事業は立ち行かなくなってしまいます。特に中小規模の建設会社では、大企業に比べて資金調達の選択肢が限られるため、より一層の注意が必要です。建設業界特有の商慣習として、完成までにかかる期間が長く、工事代金の入金までタイムラグが生じることが多いため、資金管理が非常に重要になります。
資金繰りが悪化する主な原因として、売上はあるのに手元に資金がない黒字倒産が挙げられます。売掛金の回収が遅れたり、予期せぬ出費が発生したりすることで起こります。こうした事態を避けるためには、日々の資金の流れを正確に把握し、将来のキャッシュフローを予測する経営管理が不可欠です。具体的な失敗事例を知ることで、同様の過ちを未然に防ぎ、健全な経営を維持するための対策を講じることができます。
具体的に建設業の資金繰りで失敗する事例と避けるべき行動は、以下のとおりです。
それぞれ順に解説します。
利益率の低い案件受注が資金繰りを圧迫してしまう
建設業における資金繰りの失敗で最も多いのが、利益率の低い案件を安易に引き受けてしまうケースです。特に新規顧客の獲得や他社との競争に勝つために、無理な低価格で受注してしまうことが原因となります。一見多くの案件をこなしているように見えても、それぞれの利益が薄いため、売上高は増加しても手元に残る現金が増えないという状況に陥ります。
さらに、予期せぬ追加工事や資材の高騰といった事態が発生した場合、採算割れのリスクが非常に高まります。例えば、受注額が1000万円の工事で、材料費や人件費などの原価が950万円だった場合、利益は50万円にしかなりません。追加の原価が30万円かかれば、利益はわずか20万円にまで圧縮されます。
このような状況が続くと、次の工事に必要な資材の購入資金や、従業員への給与支払いが困難になり、最終的には事業の継続が難しくなります。リスクを避けるためには、受注前に綿密な原価計算を行い、適正な利益を確保できるかどうかの判断を厳格に行う必要があります。安易な価格競争に巻き込まれず、自社の技術力や付加価値をアピールすることで、利益率の高い案件を確保する戦略が求められます。
材料費や労務費の価格変動リスクを見落としてしまう
建設工事における原価の大部分を占めるのが、材料費と労務費です。市場の動向や社会情勢によって常に変動しており、リスクを見落とすと資金繰りを一気に悪化させる原因となります。例えば、ウッドショックやコロナ禍のような世界的なサプライチェーンの混乱は、木材や鋼材の価格を急騰させています。
また、人手不足による人件費の高騰も、近年顕著な傾向と言えます。価格変動を予測せずに見積もりを作成してしまうと、工事中に原価が大幅に増加し、当初の利益計画が崩壊してしまうことになります。特に工期が長期間にわたる大規模な工事では、契約時点と工事完了時点での価格差が大きくなる可能性が高いため、リスク管理は非常に重要です。事前にリスクを避けるには、資材価格や人件費の市場動向を常に情報収集し、見積もりに変動リスクを織り込むことが不可欠です。
具体的には、資材価格の変動リスクを顧客と共有する取り決めを契約書に盛り込んだり、価格変動条項を設けたりなどの対策が有効です。特定のサプライヤーに依存せず、複数の仕入れ先を確保しておくこともリスク分散につながるでしょう。
楽観的な入金予測で資金不足に陥ってしまう
建設業の資金繰りで失敗するパターンとして、楽観的な入金予測による資金ショートが挙げられます。建設工事では、着工金、中間金、完工後の残金というように、工事の進捗に応じて代金が分割して支払われる商習慣が一般的です。
しかし、顧客の都合や予期せぬトラブルによって入金が遅れるケースは少なくありません。例えば、顧客側の支払手続きの遅延や、工事の仕上がりに不満があると主張され、残金の支払いが滞るリスクがあります。これらの状況に陥ると、当初見込んでいた入金が予定通りに行われず、その間の運転資金が不足してしまいます。
具体的には、次の工事の材料費や、当月の従業員への給与、下請け業者への支払いができなくなる事態につながります。資金繰り計画を立てる際は、入金日を確実なものと決めつけず、万が一の遅延も想定した上で、余裕のある資金計画を立てることが重要です。
リスクを防ぐためには、入金サイクルを事前に明確に顧客と合意し、契約書に明記することが不可欠です。入金が遅れた場合のリスクに備え、手元資金に余裕を持たせることや、いざという時に利用できる短期的な融資枠を確保しておくことも有効な対策となります。
税金や社会保険料を滞納して信用失墜してしまう
資金繰りが厳しくなると、目先の支払いを優先するあまり、税金や社会保険料の支払いを後回しにしてしまう会社が見受けられます。しかし、それは絶対にやってはいけない行動です。税金や社会保険料の滞納は、企業の信用を著しく損なう行為です。滞納が続くと、税務署や年金事務所から督促状が届き、それでも支払わない場合は、財産の差し押さえが行われる可能性があります。銀行などの金融機関は、企業の経営状態を判断する際、公的な負債の支払い状況を非常に重要視します。
税金や社会保険料の滞納履歴があると、融資の審査に通りにくくなり、事業拡大のための資金調達や緊急時の資金繰り支援を受けることが非常に困難になります。
また、建設業では、元請け企業が下請け企業の経営状況の厳しいチェックが行われるケースが一般的です。滞納情報が発覚すれば、元請け企業との取引停止につながる可能性もあります。税金や社会保険料の支払いを常に最優先事項として捉え、資金繰り計画に確実に組み込むことが重要です。支払いが困難になりそうな場合は、滞納する前に、税務署や年金事務所に相談し、分納の相談をするなどの対応を検討しましょう。
建設業の資金繰りに関するよくある質問の回答
- 建設業に必要な運転資金はいくらでどう計算するの?
-
建設業に必要な運転資金の目安は、「(売上原価+販売費及び一般管理費)÷12カ月×3~6カ月分」で計算できます。建設工事の入金サイトが長い点を考慮した一般的な目安です。例えば、月々の経費が500万円の場合、少なくとも1500万円から3000万円程度の運転資金が必要になります。
工事の着工から入金までの間の人件費、材料費、外注費などの支払いに充てられます。資金が不足すると、工事が中断したり、下請け業者への支払いが滞ったりするリスクが生じます。自社の事業規模や受注サイクルの特性を考慮し、この計算式を参考に適切な運転資金の目安を把握しましょう。
- 資金繰り表はどう作成する?キャッシュフロー計算書とは何が違う?
-
資金繰り表は、将来の資金の流れを予測するための社内管理ツールです。「期首残高+入金予定-出金予定=期末残高」という形で、1か月~数か月先までの資金状況を見える化します。これにより、資金ショートのリスクを事前に把握し、融資相談や支払条件の交渉などの対策が可能になります。
一方、キャッシュフロー計算書は決算書の一部であり、過去の資金の流れを「営業活動」「投資活動」「財務活動」に区分して示すものです。金融機関や投資家に提出する財務資料としての役割を持ちます。つまり、資金繰り表は未来の資金管理、キャッシュフロー計算書は過去の資金分析と位置づけられ、それぞれの役割を理解して併用することが重要です。
- 建設業のキャッシュフロー計算書はなぜ資金繰り管理に必要なの?
-
キャッシュフロー計算書は、会計上の利益と実際の資金の流れのズレを明確にするため、資金繰り管理に不可欠です。建設業では、完成工事高として売上が計上されても、代金の回収が遅れることが頻繁にあります。損益計算書上は利益が出ていても、手元に現金がないと黒字倒産のリスクを抱えることになります。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によるキャッシュフローを通じて、本業でどれだけの現金を稼ぎ出しているかを把握できます。
また、投資活動や財務活動のキャッシュフローを見ることで、設備の購入や借入金返済が資金繰りに与える影響を正確に分析できます。
- 建設業の短期運転資金と長期運転資金はどのように違うの?
-
建設業における運転資金は、短期運転資金と長期運転資金に分けられます。短期運転資金は、日常的な事業活動に必要な資金であり、材料費、人件費、下請け業者への支払いなどに充てられます。通常、工事代金の入金によって回収されるため、比較的短期間で循環します。
一方、長期運転資金は、事業拡大や新たな投資に必要な資金で、機械や車両の購入、新規事業への参入などに使われます。短期間で回収できるものではなく、銀行からの長期借入金や自己資金で賄うのが一般的です。資金繰りを考える際には、両者のバランスを考慮し、適切な資金調達計画を立てる必要があります。
- 建設業特有の手形リスクや入金遅延にはどう対応すべきか?
-
建設業特有の手形リスクや入金遅延には、事前の対策が不可欠です。手形決済は、換金までに時間を要するだけでなく、手形が不渡りになるリスクがあります。手形による支払いを可能な限り避け、現金払いの交渉が望ましいです。
入金遅延には、契約段階で支払サイトを明確に定めることが重要です。万が一遅延が発生した場合は、速やかに顧客に連絡を取り、状況を確認しましょう。
また、遅延損害金の条項を契約書に盛り込むことで、牽制効果も期待できます。ファクタリングなどの売掛債権を早期に現金化するサービスを利用することも、資金繰り改善の有効な手段と言えるでしょう。